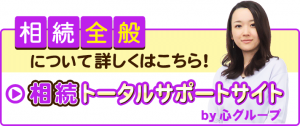離婚したときの配偶者への「相続させる」遺言書
こんにちは
朝家を出ると少し肌寒く感じるようになってきました。
名古屋にもそろそも秋が来るのかなと思います。
今回は、名古屋で働く弁護士として気になって調べたことのメモの代わりに記事を書こうと思います。
遺言書を買いて、配偶者に財産を遺す内容の遺言書を書いたものの、遺言書を書いてから長い期間が経つうちに関係がうまくいかなくなり、離婚する、というようなことがあり得ます。
このような遺言書で配偶者に対し「相続させる」遺言書を作成した後で、離婚した場合その遺言書をそのままにしておりも問題ないのでしょうか。
このポイントは
①遺言書とは違う内容の処分を遺言者が行うとその処分に関する部分の遺言は撤回したものとみなされること(民法1023条2項)
②法定相続人に対しては「相続させる」の文言で問題ないが、離婚し、法定相続人でなくなると、原則「遺贈する」文言になること
③遺言書は遺言者の真意を探求すべき(最高裁判所昭和58年3月18日判決)
ということです。
別に財産を処分しているわけではなく、遺言書で書かれた人は通常生年月日や作成時の関係性(配偶者や子、長男、孫など)で特定されていますので、遺言書を書いた後で離婚しても別人になるわけではないので、遺言書とおりに相続されるように思われます。
一方で、配偶者だからこそ「相続させる」としていたのだから、配偶者でなくなった以上は相続できないとの考え方もできます。
通常、遺言者の真意としても離婚した相手に財産を遺す意思があったのか疑問になることも多いでしょう。
この点について学説上や実務上も明確な回答がなされておらず、事案毎に「遺言者の真意を探求」して判断がなされているようです。
※離婚した相手に「相続させる」遺言では「遺贈」に趣旨は含まれず、相続を認めないとした東京地裁の判決があります(東京地方裁判所平成22年10月4日判決)。
そのため、自分が配偶者に「相続させる」遺言書を書いており、離婚した配偶者に遺産を遺したくない(あるいは逆に離婚していたとしても財産を遺したいと)と考えているのであれば、遺言書を撤回して、最新の自分の意思を明示した遺言書を作成することが重要です。
遺言書は最新の遺言書が優先されるので、離婚後の意思が明確な遺言者があればそちらが優先されます。
遺言書は一度作れば終わりというものではなく、自分の生活状況に併せて常に更新していくことが重要です。
離婚のような自分の相続人の関係性が変更したときなどは特に見直しが重要になります。
本日はここまでとさせていただきます。
また次回お会いしましょう。